
症例55
【症例1】80歳代男性
画像はこちら
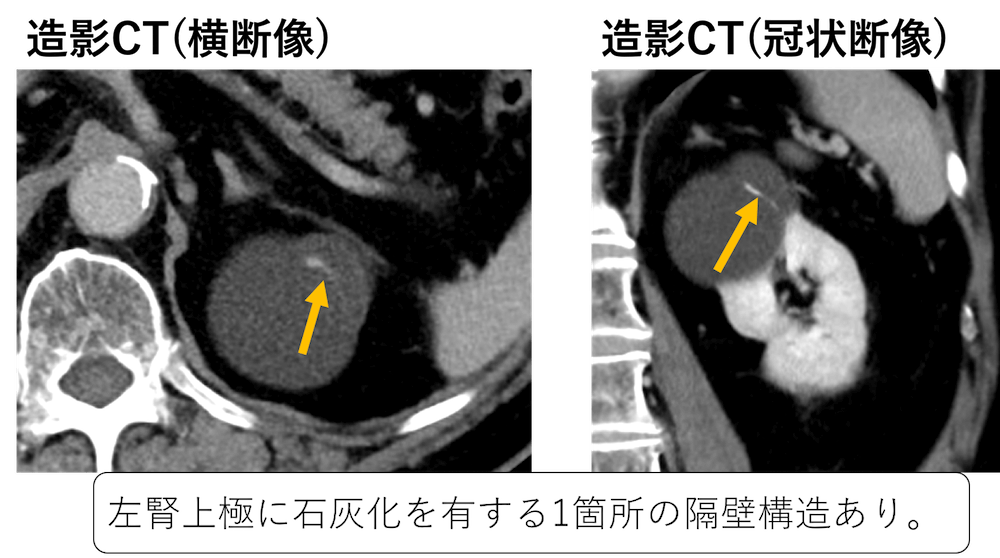
左腎上極に石灰化を有する1箇所の隔壁構造を認めています。
嚢胞は2房性です。
嚢胞壁に不整な壁肥厚や壁在結節を疑う所見を認めません。
これは、bosniak分類Ⅱ相当の嚢胞となります。
【症例2】50歳代男性
画像はこちら
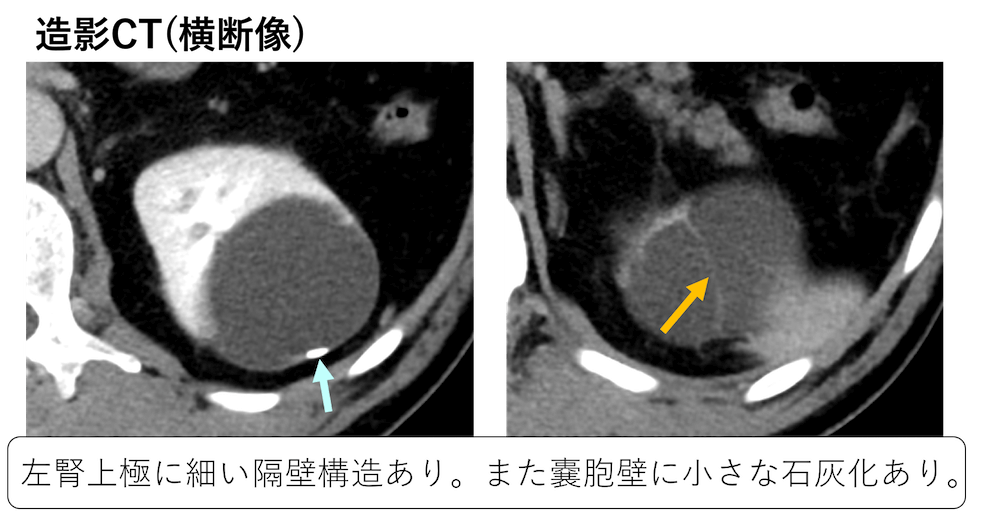
同じように左腎上極に1箇所の隔壁構造を認めています。また嚢胞壁に小さな石灰化を認めています。
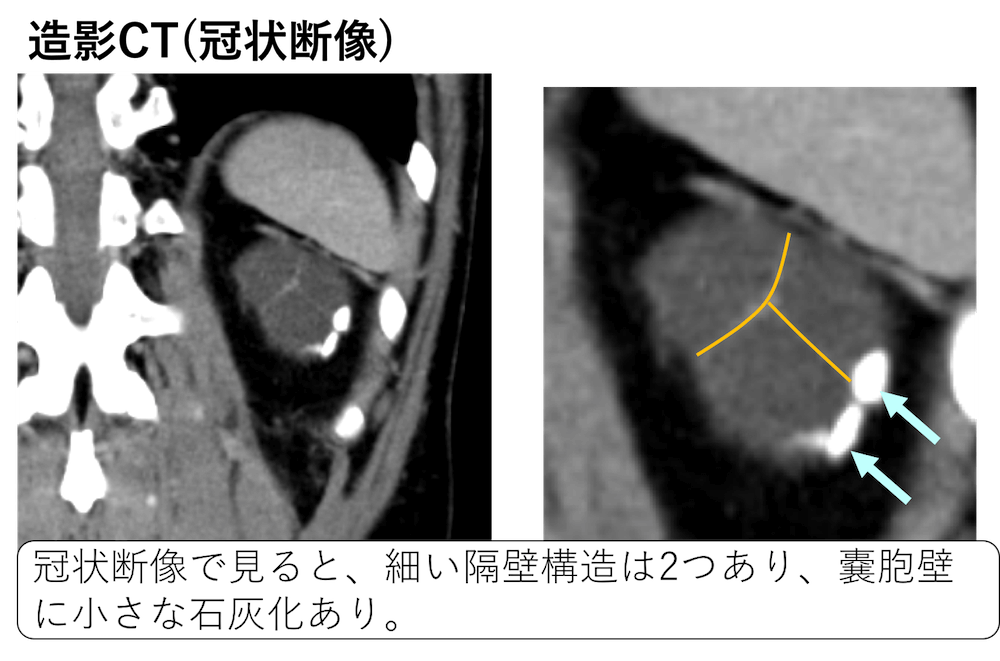
冠状断像で見ると、隔壁構造は1つではなく、2つあることがわかります。
嚢胞壁に不整な壁肥厚や壁在結節を疑う所見を認めません。
これも、bosniak分類Ⅱ相当の嚢胞となります。
bosniak分類Ⅱ相当の嚢胞とは?
2つ以下の薄い隔壁をもち、わずかな石灰化を有することもある嚢胞です。
あるいは、3cm以下の高吸収嚢胞がこれに該当します。
診断:腎嚢胞(bosniak分類Ⅱ)
関連:
お疲れ様でした。
今日は以上です。
今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

Bosniak分類はすぐ忘れてしまうので表で確認するようにしています。
そうですね。
覚える必要はないかと思います。(覚えられればそれに超したことはないですが)
表などで常に確認できるようにしておくべきですね。
壁肥厚と造影効果の合わせ技1本でカテゴリー3なんですね。ここがあやふやでした。ありがとうございました。
アウトプットありがとうございます。
カテゴリー分類は悩ましいケースもありますが、明確な場合は分類しやすいですね。
ワニノコ1は、単純がないと「石灰化」なのか「造影効果」なのかわかりずらかったです。
ワニノコ2は、隔壁がどの程度までが「薄い隔壁」なのか、「肥厚」なのか、自分の中でまとまっておらず、今回勉強になりました。
アウトプットありがとうございます。
おっしゃるように単純+造影で厳密には判断したいところですね。
3cm以上ならⅡFというのは高吸収嚢胞の場合のみなんですね、勘違いしていました。
アウトプットありがとうございます。
なかなか覚えられないですよね。怪しい腎嚢胞を見たら、都度表に戻るでもよいかもしれませんね。
こんにちは!いつもお世話になっております。
恥ずかしながらBosniak分類初めて知りました!
コメント欄を見るとみなさん当たり前のようにご存知のようで、しっかり勉強しておきます!
アウトプットありがとうございます。
「これはBosniak分類のⅡ相当ですね」
と言う学生の先生や研修医の先生がいたらびっくりします。いや、引きます(^_^;)
ある程度有名ではありますが・・・・
これはやばい(悪性の可能性がある)腎のう胞なのか、それともフォローの必要さえない単なる単純性腎嚢胞なのか
の指標となる分類です。
どういった所見があればやばい(悪性の可能性がある)腎のう胞なのかをまずは押させておきましょう!
腎のう胞は、他の目的で撮影された単純CTで機会的に認めるケースは正直多く、全例に造影というのはrecommendできません。こういった実臨床でBosniakを造影の部分はヌキで使うというのもアリなのでしょうか?
アウトプットありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。
怪しいものは単純CT+エコーでフォローでも良いと思います。
大事なのはbosniakに当てはめることではなく、腫瘍化している・もしくはしそうな嚢胞を引っかけることですので。
症例1のSMAの中域(膵臓の下縁レベル)で脂肪濃度が少し上がっていますが、これは異常所見ですか?
アウトプットありがとうございます。
おっしゃるように腸間膜の脂肪織濃度上昇を認めていますが、通常はよくある非特異的所見として扱われます。
ただし、腹痛など症状がある場合は腸間膜脂肪織炎の可能性もあり、注意が必要です。
症状があるかないか、過去画像があればそれとの比較が大事な所見となります。
Bosniak分類は私も初めて知りました。
腎嚢胞を見たときに意識するようにします。
Ⅲ、Ⅳは確かに悪そうな顔をしていますね。
アウトプットありがとうございます。
ほとんどは単純性で経過観察の必要もないのですが、単純性とそうでないものがありますので、特にⅢ、Ⅳには注意が必要です。
隔壁が2つ、ということは、3嚢胞まではフォロー不要ということですか?
それとも、嚢胞が、3つにわかれていればフォロー対象でしょうか?
アウトプットありがとうございます。
嚢胞内に隔壁を認めることがありますので、嚢胞がいくつというわけではありません。
いつも勉強になる症例を有難うございます。
普段偶発的に見かけるのは、カテゴリーⅠ相当の単純性腎嚢胞が多いのでbosniak分類をほとんど意識しておりませんでした。怪しい嚢胞は症例数こなさないと、カテゴリー分類するのが難しいと感じました。
厳密には、小さなcomplicated cystでもカテゴリーⅡなのですね。私の病院で3cm以下のcomplicated cystをカテゴリーⅡと書いてくれているレポートは見かけないのですが、それ程度だと省略するケースが多いのでしょうか?実際はⅡF以上が臨床上重要だからでしょうか。
ご提示された2症例目は石灰化が大きいと感じⅡFと回答してしまいましたが、どこまでの厚みのある石灰化からⅡFとすべきでしょうか?そこは主観要素が強いですか
あと、「人」の字状の隔壁数は2なのですね。慣れていないので2か3か悩みました。因みに数学で書くような丸みのある「x」字状の場合は隔壁数いくつですか?(^o^;)
長々となり、すみませんがご教授お願い致します。
アウトプットありがとうございます。
>厳密には、小さなcomplicated cystでもカテゴリーⅡなのですね。私の病院で3cm以下のcomplicated cystをカテゴリーⅡと書いてくれているレポートは見かけないのですが、それ程度だと省略するケースが多いのでしょうか?実際はⅡF以上が臨床上重要だからでしょうか。
そうですね。サイズが小さいものは単にcomplicated cystとのみ記載することが多いです。
>2症例目は石灰化が大きいと感じⅡFと回答してしまいましたが、どこまでの厚みのある石灰化からⅡFとすべきでしょうか?そこは主観要素が強いですか
主観要素も強いですね。確かに石灰化を結節状と取る方もおられる微妙なところです。
>あと、「人」の字状の隔壁数は2なのですね。慣れていないので2か3か悩みました。因みに数学で書くような丸みのある「x」字状の場合は隔壁数いくつですか?(^o^;)
これもケースバイケースですので、各症例をいろんな角度から観察しないと一概には言えないですね。