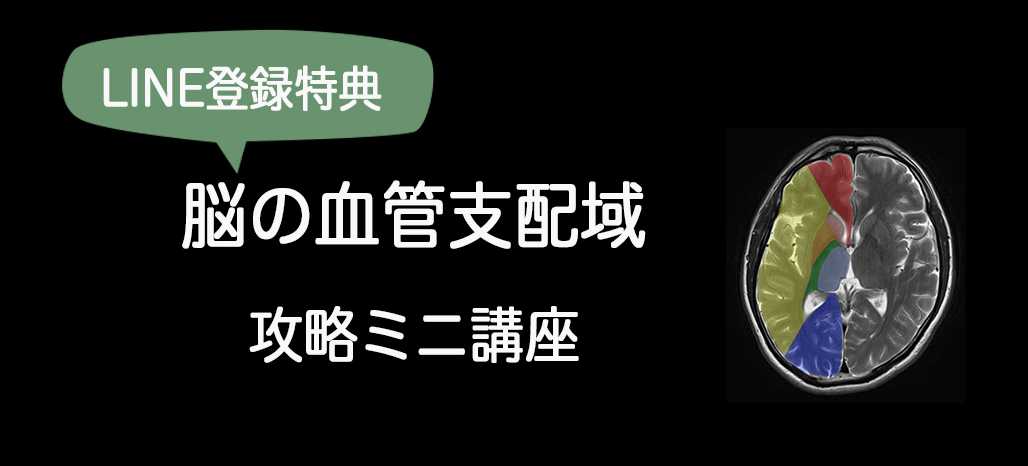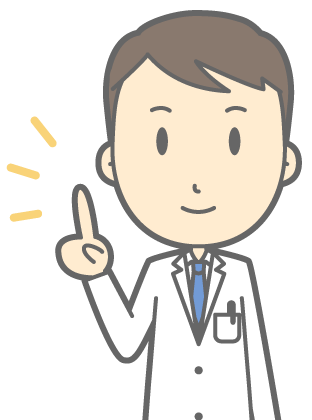CT検査をした後に、妊娠していることが判明したり、妊娠していることがわかっている中、どうしてもCT検査が必要なこともあります。
CTは被曝をしますので、胎児への影響がまず懸念されます。
そこで今回は、CT検査がどの程度胎児へ影響するのか?をまとめました。
妊婦のCT検査による胎児への影響
まず結論
妊娠に気付かずにCTを撮影した場合、みなさん心配されるところですので、まとめておきましょう。
その前に、女性患者さんにCTを撮影するときは、必ず妊娠の可能性を考慮し、問診しましょう。
関連記事)
1回のCTで胎児の被ばく量は?
当然、母体がどこの部位のCTを撮影するかで異なります。まとめた表が以下です。
| 検査 | 平均線量(mGy) | 最大線量(mGy) |
| 頭部CT | 0.005以下 | 0.005以下 |
| 胸部CT | 0.06 | 0.96 |
| 腹部CT | 8 | 49 |
| 骨盤CT | 25 | 79 |
(ICRP Publication 84.Ann ICRP 30:1-43,2000)
これは、国際放射線防護委員会(ICRP)で次のように言われているためです。
その根拠として胎児被ばくの確定的影響として、精神発達遅滞・奇形発生の閾値が100mGyであるからです。
これはつまり、「100mGy以上被ばくすると、1-5%の胎児が、精神発達遅滞・奇形発生を起こす」ということを意味します。
逆に言えば、100mGy以下では、そのようなことが起こる証拠がない。ということです。
つまり、100mGy以下の被ばくであるならば、被ばくした胎児と、していない胎児との間に、精神発達遅滞や奇形が発生する確率に有意な差が見られないということです。
2008年には、16列CTによる1回の腹部・骨盤CT撮影での胎児被ばく量は、平均10.8mGyと報告されています(Radiology 249;220-227, 2008)
むやみに撮影して被ばく量を増やしてはいけません。
いくら機械が進歩して被ばく量が減ったとはいえ、2回以内の撮影にしたいところです。
実際、「産婦人科診療ガイドライン;産科編2011」(日本産婦人科学会)では、安全を見込み、50mGyを放射線被ばく安全限界としているくらいです。
参考)妊娠中の放射線被曝の影響について
- 被曝時期を慎重に決定し、説明する。
- 受精後10日までなら奇形発生率は上昇しない。
- 受精後11日〜妊娠10週でも50mGy未満では奇形発生率を上昇させない。
- 妊娠10~27週では、中枢神経障害の危険性があるが、100mGy未満では影響しない。
- 個人レベルでの発がんリスクは極めて低い。
(産婦人科診療ガイドライン 産科編2011より引用)
ご案内
腹部画像診断を学べる無料コンテンツ
4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ
1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。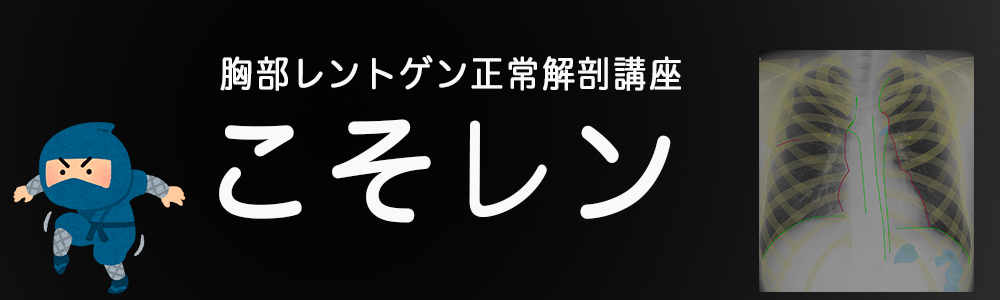
画像診断LINE公式アカウント
画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。