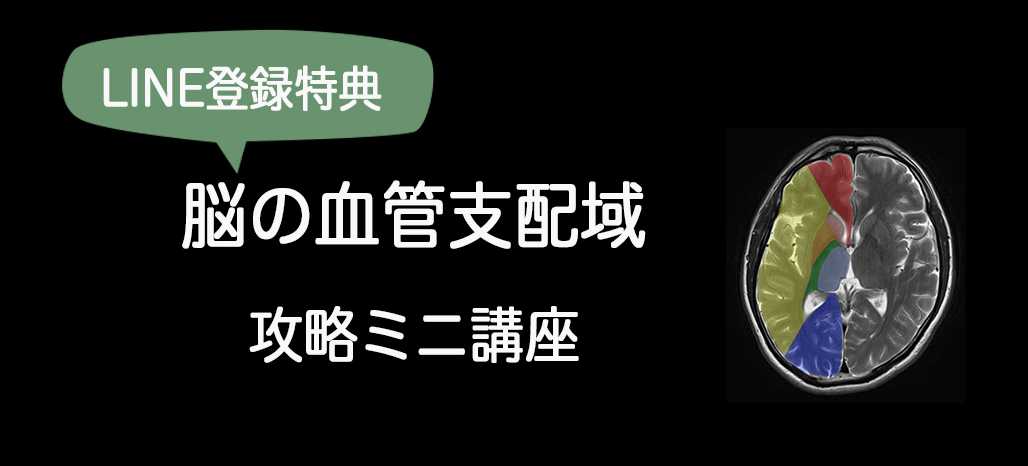Ⅰ期非小細胞肺癌に対する定位放射線治療
・治療後、完全に消失する症例は10%以下。
・普通は、肺炎様になった後、収縮性変化が残る。中にはdenseが大きな陰影が残り、LKとの画像での鑑別は困難なことがある。
・定位放射線治療の患者は年々増えている。
・治療成績の報告にはばらつきがある。大きさと線量による。アメリカでは子宮頸癌などでもそうだけど、線量が多い。サイズ小さくて線量大きければ制御よい。ただし、局所コントロールは90%前後でできており、報告によるばらつきは少ない。
・日本では12Gyの4回法を用いる(48Gy/4fr)のがメイン。
・日本での後向き研究では、100Gy以上で局所制御は良好。(BED:biological effective doseは100Gy以上ということ)。
・有害事象は放射性肺臓炎(radiation pneumonitis)が最多、他、肺胞出血、食道炎など。
放射性肺臓炎の注意点
・時間がかなり経過したあとで出てくることがある。
・一旦消えた後、再び出てくることがある。
・肝の直上に放射線を当てた場合、肝転移のように肝に変性が起こることがある。
・特に肺線維症はリスクファクター。他に、線量が多かったり、中心型のLK(閉塞性肺炎起こしたり、大血管傷つけたりする)にはリスクが高い。
・末梢型のLKでは肋骨骨折が半分の患者に起こる。症状あるのはその半分。骨転移と間違えないように。他には、胸壁に炎症が生じることがある。
・COPD患者では手術とSABRは5年生存率に差がない。むしろRTの方が良い。なので手術できる人にも代替となりえる。
ご案内
腹部画像診断を学べる無料コンテンツ
4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ
1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。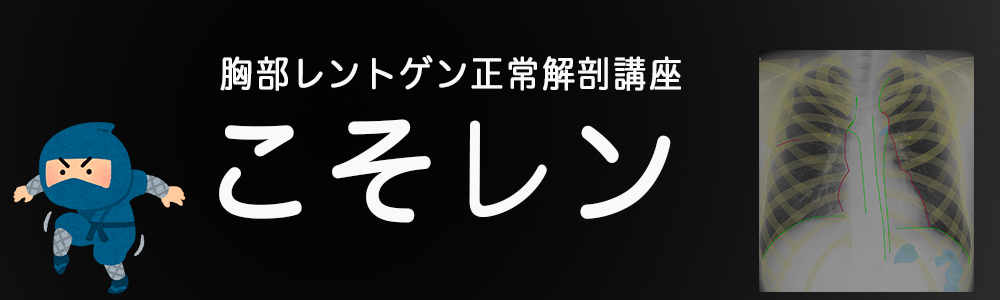
画像診断LINE公式アカウント
画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。