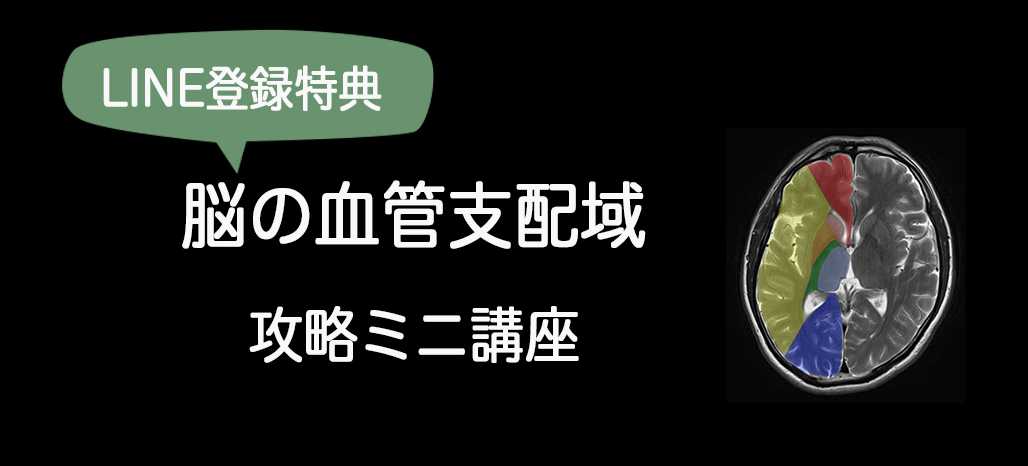巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)(giant cell arteritis/temporal arteritis)
- 主に50歳以上の高齢者に発症する中型および大型の動脈の炎症。
- 家系内集積の例も報告されており、 HLA-DR4との関連が指摘されている。
- 頸動脈の分岐を1つ以上障害することを特徴とし、特に側頭動脈が多い。ただし、全身疾患であるので注意。病変の主座は頚部より末梢の血管。側頭動脈以外にも、頸動脈の頭蓋外の分枝である浅側頭動脈、後頭動脈、顎動脈、眼動脈のほか、椎骨動脈に見られることがある。
- そのため、側頭動脈炎と呼ばれていたが、最近では、巨細胞性動脈炎(GCA:giant cell arteritis)と呼称する。
- 徐々に発症し、症状の完成に数カ月~1年余を要する。
- リウマチ性多発筋痛症(polymyalgia rheumatica)との合併が多い。
- 発熱、貧血、頭痛を主訴とする。 典型的には浅側頭動脈の炎症に伴う側頭部痛、顎動脈虚血に伴う顎跛行(咀嚼運動に伴う疼痛)などを伴うことあり。
- 虚血性眼症状(虚血性視神経障害)の合併が重要で、治療がなされないと失明に至る。そのため、本疾患を疑うことが重要。
- リウマチ性多発筋痛症は、頚部、肩、下背部、殿部および大腿の筋肉のこわばり、うずき、疼痛を特徴とする。
- 採血では血沈亢進・CRP高値・血小板の増多が有名で、組み合わせで高い感度・特異度を示す。
- 椎骨動脈狭窄や胸部大動脈瘤の合併頻度が高い。
- 確定診断は側頭動脈の生検がなされる血管の病変は分節状であることもあるため、3~5 cmの生検材料を採取し、連続した断面を生検標本とすることにより、診断率を上 げることができる。 生検前の画像診断は炎症の局在の同定に寄与する可能性がある。
巨細胞性動脈炎の分類基準(米国リウマチ学会)
以下5項目のうち3項目以上を満たすときに巨細胞性動脈炎と分類する。
- 発症年齢が50歳以上
- 新たに生じた頭痛
- 側頭動脈の異常(拍動性圧痛あるいは脈拍減弱)
- 赤沈の亢進:50mm/h以上
- 動脈生検組織の異常(単核嗅細胞の浸潤または肉芽腫を伴う炎症があり、多核巨細胞を伴う)
巨細胞性動脈炎の画像所見
- エコーにおける、血管周囲のhypoechoic haloの所見の特異度が高い。
- MRIでは、浅側頭動脈の炎症を反映して、T2強調像・造影T1強調像で高信号に描出される。
- 浅側頭動脈は脂肪織内を通過するため、脂肪抑制を加えることが必要。ただし、脂肪抑制のシーケンスは本疾患が検査前に疑われないと基本的には、撮像されない。
- DWIにおいて高信号になることあり。頭部皮下の非特異的な結節様高信号との鑑別は重要。
- PET-CTで血管壁に集積を認め早期発見が可能だが、保険適応外。
血管炎による脳梗塞を起こす疾患
- ベーチェット病
- SLE
- 結節性動脈炎
- 巨細胞性動脈炎
参考)
- 臨床画像2013年10月増刊号 症状からアプローチする画像診断 P20
- 参考文献)これだけは知っておきたい心臓・血管疾患の画像診断 P304-5
ご案内
腹部画像診断を学べる無料コンテンツ
4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ
1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。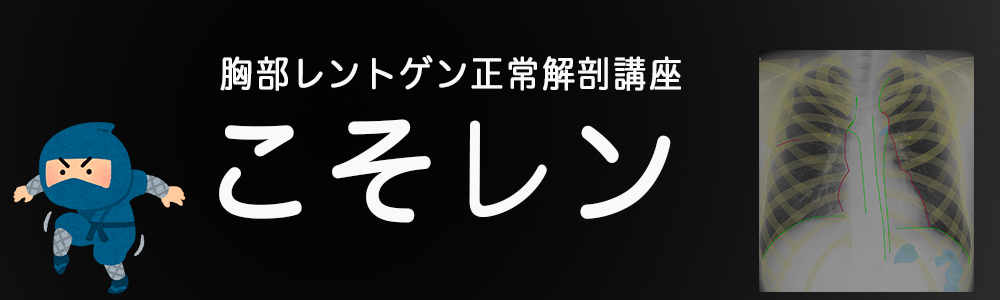
画像診断LINE公式アカウント
画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。